来月、友人や会社の同僚たちと日帰り登山をする予定だけど、何を持って行けばいいのかわからない……そんな初心者の不安な気持ちよく分かります。
そこで今回は、安全性を第一に考えたうえで、ユニクロやワークマン、100円ショップなど身近なショップでも手に入る、コスパの良い登山持ち物を厳選して紹介します。
登山経験者の視点から、「必要なもの」と「代用できるもの」の線引きを明確にし、安心・快適な登山デビューをサポートします。
「これがなきゃ始まらない」登山の三種の神器

登山初心者がまず揃えるべきは「三種の神器」と呼ばれる基本装備。安全性と快適さの要となるこの3点は、慎重に選びたいアイテムです。
登山靴は“足元の命綱” 靴選びが山の安全を決める
登山では、歩行中の滑落や捻挫といった足元のトラブルが命取りになることも。だからこそ、靴選びは最重要ポイントの一つです。理想は、防水性とグリップ力に優れたローカット〜ミドルカットの登山靴。ただし、低山や整備された登山道であれば、トレイルランニングシューズや滑り止め付きのスニーカーでも代用可能です。
靴下は厚手の登山用ソックスが理想ですが、ユニクロなどのスポーツ用クッション入りソックスも使えます。大切なのは「靴と足がフィットしているか」「長時間歩いても痛みや靴擦れが起きにくいか」という点。可能であれば実店舗で試し履きし、靴下もセットで合わせることをおすすめします。
ザック選びで差がつく!収納力と快適性の黄金バランス
登山中に両手を空けておくことは、安全確保の基本です。そのためには、体にしっかりフィットする登山用ザックの使用が欠かせません。日帰り登山なら、最低限の容量は20〜30Lが目安。収納ポケットが多く、チェストベルトやウエストベルトが付いたものを選ぶと、荷重が分散されて疲れにくくなります。
代用品として、アウトドア用途をうたったリュックであればワークマンや無印良品にも選択肢があります。ただし、背面にパッドがないものや、肩ベルトが細すぎるものは避けたほうが無難です。雨天や朝露に備えて、100円ショップのザックカバーや大きめのビニール袋を活用するのも一案です。
雨は想定内!レインウェアで山の天気を攻略せよ
山の天気は変わりやすく、晴天でも急な雨に見舞われることがあります。そのため、レインウェアは必ず上下セパレートタイプを準備しましょう。ポンチョやビニールカッパは風に弱く、登山中の動作を妨げるため不向きです。
レインウェアは、防水性・透湿性・軽量性のバランスが大切。ノースフェイスやモンベルなどのアウトドアブランド製が理想ですが、ワークマンには防水加工+動きやすさを備えた優秀な製品が揃っています。上下セットで3,000円前後と手頃な価格帯も魅力です。サイズはやや余裕のあるものを選ぶと、中間着の上から着ても動きやすくなります。
ユニクロ&ワークマンでOK?代用可能な登山ウェア事情

登山専用ウェアは高価ですが、機能を理解すれば代用品も有効。体温調整と汗処理が快適さと安全性を左右するポイントです。
“綿NG”は本当?汗冷えしない登山インナーの選び方
「綿のTシャツは登山に不向き」とよく言われるのですが、正確には“濡れたままの綿を着続けると体が冷える”のが問題です。汗をかいた後にそのまま休憩すると、急激に体温が奪われるリスクがあります。綿自体が悪いのではなく、使い方が問われる素材です。
一方、化学繊維の吸汗速乾インナーは汗を素早く逃がしてくれますが、肌が敏感な人や体臭が気になる人にとっては、化繊のニオイや肌刺激が気になることも。その場合には、肌触りの優しいコットンのインナーにして、汗をかいたら着替えられるように着替えの枚数を多めに持っていくのも現実的な選択肢です。
自宅から着ていく1枚、山頂など長時間の休憩時に着替える1枚(ひと目が気になることもあると思いますが、濡れたままよりは快適)、下山して帰宅時に着る1枚があれば最低限はまかなえるでしょう
ベストバランスはメリノウール素材のインナー。天然素材で吸湿性・防臭性・保温性に優れており、化繊とコットンの中間的な機能を持ちます。ただし高価なため、本格的な登山でない限りは、普段から愛用しているコットンのインナーでも構わないと個人的には思います。
防寒対策はレイヤリングが鍵!軽量ダウンの実力とは
低山でも朝晩は冷え込みます。特に標高1,000mを超える場所では、体感温度が10℃以上低くなることもあります。そんなときのために、薄手で軽量な保温着は1枚持っておきたい装備です。また、気温は100mごとに0.6度ほど低くなるため、自分が登る山頂の標高を事前に調べておいて、山頂の気温にあった服装を用意しておきましょう。
防寒対策は“レイヤリング(重ね着)”が基本。ベースレイヤーの上にミドルレイヤー(保温層)として、フリースやダウンを重ねます。ユニクロのウルトラライトダウンは携帯性が高く、気温調整がしやすい定番アイテム。ワークマンのフリースも低価格ながら機能性が高く、コスパ重視の初心者には心強い存在です。
また、ザックに収納しやすい収納袋付きの製品を選ぶと、気温変化に合わせてこまめに着脱でき、汗冷えや過剰発汗を防げます。
フェイスタオルにもひと工夫!快適さは汗対策から
登山中の汗対策は見落とされがちですが、実は快適さに大きく関わる要素です。首にかけるフェイスタオルや汗拭きタオルには、吸水速乾性のある素材を選びましょう。
ユニクロや無印良品では、薄手で軽量かつ速乾性に優れたタオルが手に入ります。さらに100円ショップでもマイクロファイバー素材のタオルが購入可能で、登山用として十分な機能を持っています。
タオルは汗の拭き取りだけでなく、首の日焼け防止や冷却グッズとしても活躍。登山後の顔拭き・手拭きにも使えるため、2枚ほど持参しておくと便利です。コンパクトに折りたためる素材を選ぶと、ザックの収納スペースも圧迫しません。
遭難回避のカギはこの3つ!水・食・光の備え

水分・エネルギー・視界。登山で命に関わる3要素を確保することが、安全な行動の第一歩です。
「喉が渇く前に飲め」脱水対策は行動力を左右する
登山中は思っている以上に汗をかき、水分の消費量も増えます。「喉が渇いた」と感じたときにはすでに脱水が始まっていることも。そこで重要なのが、こまめな水分補給です。
一般的には、日帰り登山でも最低1〜1.5リットルの水分を持参するのが理想。500mlペットボトルを数本に分ける方法もあるほか、飲み終わると丸めて保管できるやわらかいソフトボトル製のウォーターボトルなら軽量で荷物もかさばりません。無印良品のシリコンボトルや100円ショップの水筒カバーなど、実用的な選択肢も増えています。
さらに、夏場や急登のコースではスポーツドリンクや塩飴などでミネラルも補給すると、熱中症の予防になります。飲むタイミングは「喉が渇く前に少しずつ」が鉄則です。
行動食は登山の燃料!低血糖を防ぐチョイス術
登山中は休憩ごとに少しずつエネルギーを補給する「行動食」が不可欠です。エネルギー切れによるふらつき(しゃりバテと言われてます)や集中力の低下は、転倒や道迷いといった重大事故につながりかねません。
行動食は、小分けで持ち歩けて片手で食べられるものがベスト。おすすめは、チョコレート、ナッツ類、ドライフルーツ、塩ようかん、カロリーメイト、エネルギーゼリーなど。これらはコンビニやスーパーで手軽に揃えられる上、常温保存が可能です。自宅で余計な包装紙から出しておくことや、ジップロックなどに入れ替えておくと、ゴミも出ないし重量が少しでも軽くなるのでおすすめです。
非常用として、1食分のカロリーを補える保存食(例:アルファ米、栄養バー)も1つ携行しておくと安心。低血糖を防ぐためにも、糖質を中心とした素早く吸収される食品を優先的に選びましょう。
夕暮れトラブルに備える!軽くて明るいヘッドライト術
「日帰りだからライトはいらない」と思いがちですが、山では予想外のルート変更や遅延によって下山が日没にかかるケースは少なくありません。そんなときに頼れるのがヘッドライトです。
登山用のヘッドライトは、両手が使えること、軽量であること、そして明るさが十分であることが重要な条件です。100ルーメン以上の明るさが目安で、LEDタイプが主流。乾電池式のものなら100円ショップでも予備電池を手に入れられるので、必ずセットで準備しましょう。
使用頻度は少なくても、緊急時には命を守る装備のひとつ。スマホのライトはバッテリー消費が激しいため、代用は危険です。登山の基本装備としてヘッドライトは常に持参する意識を持ちましょう。
迷わない・つながる!初心者のナビ&通信の基本
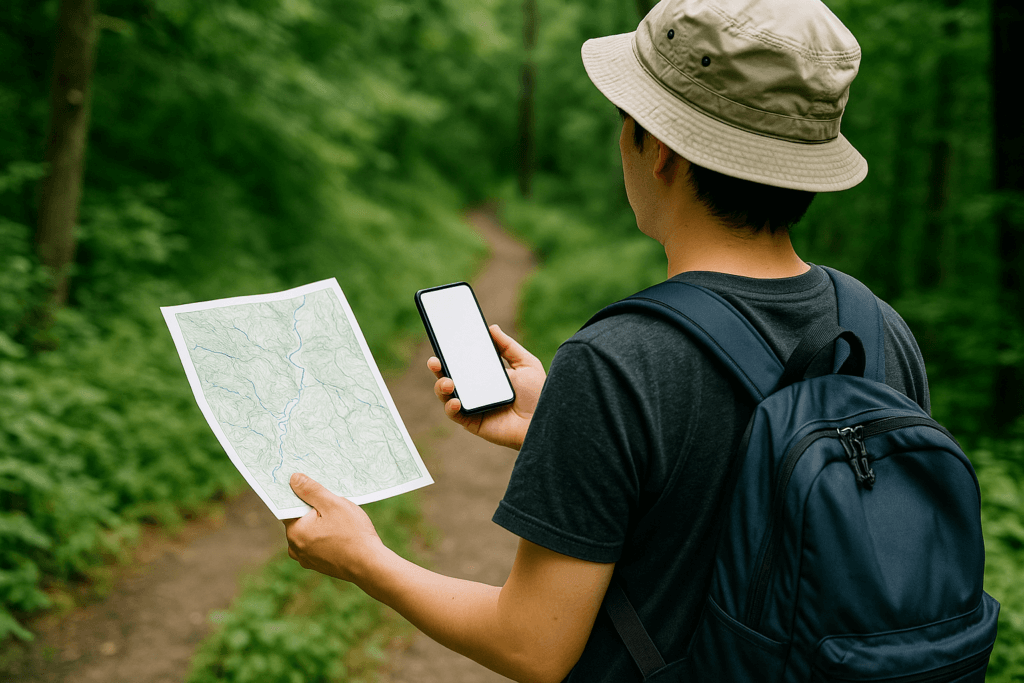
道に迷ったり、電波が届かなくなるリスクに備えるのも登山の基本。紙とデジタルを併用した“安心設計”がカギです。
紙地図?アプリ?正しい登山道の見つけ方
登山初心者が道に迷わないためには、事前準備と当日のナビゲーション体制が重要です。ヤマレコやYAMAPなどの登山アプリは便利ですが、GPSの電波が届かない場所やバッテリー切れに備えて紙地図とコンパスも用意しておくのが理想です。
初心者向けの山では、地図アプリのオフライン機能を活用すれば、通信圏外でも現在地を把握できます。しかし、アプリに頼りすぎると、トラブル時に対処できない可能性も。紙地図は登山口の観光案内所やネット通販で入手でき、100円ショップのクリアケースで防水すれば登山中も安心して使えます。
事前にルートの所要時間、エスケープルート(緊急時の下山道)もチェックし、計画性をもった山行を心がけましょう。
スマホ頼りは危険!予備電源の“安心投資”
スマホは地図、連絡、カメラ、時計と多用途に使える便利アイテムですが、長時間の使用や低温環境でバッテリーは急激に消耗します。そのため、モバイルバッテリーの持参は必須です。
おすすめは、軽量コンパクトかつ容量5000〜10000mAhのモバイルバッテリー。ケーブルとセットで防水ケースに入れておけば、雨や汗の浸水対策にもなります。無印良品や家電量販店で購入可能なモデルでも十分対応可能です。
さらに心配な人は、乾電池式の簡易充電器も予備として持っておくと安心。スマホだけに頼らず、情報源を複数用意しておくことが“山での安全策”となります。
もしもの備え!筆記グッズが命を救う場面も
登山では、思わぬトラブルで連絡が取れなくなる可能性もあります。そんなとき、筆記用具が役立つ場面が意外に多いのです。
たとえば、登山届を山小屋や登山口で提出するとき、体調不良の仲間の情報を書き残すとき、万が一の遭難時にメッセージを残すときなど。防水性のあるメモ帳と油性ペンを1セット、ジップロックなどの防水袋に入れてザックに常備しておきましょう。
100円ショップには防水用紙やミニノート、携帯ペンなどが揃っています。普段は使わないかもしれませんが、いざというときに「持っててよかった」と思える重要な備えです。
“小さな備え”が大きな安心に!応急&衛生アイテム術

ちょっとしたケガや不調も、山では大事につながります。最低限の応急処置と衛生対策で安心・安全の登山を。
ケガや靴擦れに即対応!ミニ応急セットの作り方
登山中は、靴擦れや切り傷、虫刺されなどちょっとしたトラブルがつきもの。そんなときのために、応急処置グッズをミニマムで揃えておきましょう。
基本セットとして揃えたいのは、絆創膏(大小)、消毒シート、テーピングテープ、鎮痛剤、常備薬、使い捨て手袋など。これらはドラッグストアや100円ショップで個別に購入して、自作キットにまとめるとコストも抑えられます。
さらに、化粧用の小分けポーチや無印良品の小物ケースに収納すれば、取り出しやすく整理もしやすいです。重量もかさばらないため、ぜひ携帯しておきたいアイテム群です。
帽子・手袋・UV対策で快適&安全な山歩きへ
夏の登山では、日差し対策も重要です。特に首や顔、手は日焼けしやすく、無防備な状態だと後でヒリヒリするだけでなく、熱中症リスクも高まります。
帽子はつば付きでUVカット機能のあるものを選びましょう。ユニクロやワークマンで手軽に入手できます。手袋は軍手でも代用できますが、できれば滑り止め付きのアウトドア用が望ましいです。100円ショップにも使える商品があります。
また、日焼け止めや虫よけスプレーも必需品。ドラッグストアで購入できるSPF50以上の日焼け止めや、ディート不使用の虫よけなら肌にも優しく安心して使えます。携帯用の小ボトルに詰め替えれば荷物もかさばりません。
携帯トイレと除菌対策はエチケットと命の両方を守る
山にはトイレがない場所も多く、トイレ問題は登山初心者にとって意外な落とし穴。そこで重宝するのが携帯トイレです。急な腹痛や混雑時でも、プライバシーと衛生を保ちながら用を足せる心強いアイテムです。
携帯トイレは、吸収シート入りの袋タイプが主流で、100円ショップや登山用品店で購入可能。使った後は密封できるジップ袋に入れ、必ず持ち帰るのがマナーです。
また、トイレ使用後の手洗い代わりに除菌ウェットティッシュも携行しましょう。コンパクトサイズで2~3パック持っておけば、食事前や手の汚れにも対応できます。登山では“衛生管理も安全管理の一環”として考えたいポイントです。
“あってよかった!”初心者が感動する便利グッズ
必須ではないけれど、あると驚くほど便利なアイテムたち。使って初めて「手放せない!」と実感できる装備をご紹介します。
トレッキングポールは慎重に導入を!選び方と注意点
登山初心者が最初に戸惑うのが「トレッキングポールって本当に必要?」という疑問。結論から言えば、体力や膝に不安がある人、長い下り坂に苦手意識がある人には特に有効なアイテムです。
ポールは体のバランスを保ち、膝への負担を軽減する効果があります。ただし、安価な製品(特に100円ショップの簡易スティック)は強度や伸縮機構に難があることも。万が一の破損時に転倒につながる可能性もあるため、信頼性のある製品を選びましょう。
初めは片手1本からでもOK。ワークマンやホームセンターで手に入る初心者向けモデルも選択肢になります。無理に導入せず、必要性を感じたら段階的に取り入れるのがベストです。
サングラスや虫よけ…実は忘れがちな快適装備たち
登山道で木漏れ日が強い日や、稜線で日差しを遮るものがないルートでは、サングラスの効果は絶大。特に目の疲れや紫外線対策には必須級のアイテムです。
また、虫刺され対策もお忘れなく。春〜秋にかけてはブヨやアブ、蚊などが出現するため、虫よけスプレーやシールを持参するのがおすすめです。ディートやイカリジン配合のものを用途に合わせて選びましょう。
これらのアイテムは、ドラッグストアや100円ショップで手軽に入手可能。あらかじめ小分けしてポーチにまとめておくと、いざという時にすぐ使えて便利です。
小物整理の革命!サコッシュで身軽な登山スタイルに
登山中、スマホ、行動食、地図、ハンカチなど頻繁に出し入れするものを毎回リュックから取り出すのは面倒……そんなときに便利なのがサコッシュやウエストポーチです。
サコッシュは軽量で肩掛けでき、すぐに取り出したい物を入れておけるので便利です。ユニクロ、無印良品、100円ショップなどにもシンプルで使いやすい製品があります。登山用にこだわらなくても、マチ付きでチャックがあるものなら十分に代用可能です。
リュックとの組み合わせで収納を分散でき、荷物の整理整頓もしやすくなります。ただし、貴重品を入れておくと、うっかり休憩時に置き忘れたり、思わぬ動作でなくしてしまったりすることもあるので、大切なものはなるべくリュックにいれておくのが安心です。
そもそも、なくして困るものは最低限にして、なるべく持っていかないのが無難ではあります。
“軽い・安全・コスパ良し”が初心者装備の鉄則!
日帰り登山の装備で大切なのは、何よりも「安全を確保できること」。そして、登山を続けるうえでの「快適さ」「負担の少なさ」「金銭的な継続性」も欠かせません。最初から高価な装備に頼る必要はなく、身近なお店で代用できるものを活用しながら、少しずつ自分に合ったアイテムを見つけていくことが、継続的で楽しい登山への第一歩になります。
今回紹介した装備リストを参考に、まずは安全性の高い三種の神器(登山靴・ザック・レインウェア)を中心に揃え、必要に応じて防寒・衛生・緊急対応用品を追加していきましょう。そして何より、登山は自然を楽しむアクティビティ。過不足なく、自分のペースで無理なく準備を進めていくことで、きっと安全で心地よい山時間があなたを待っているはずです。















